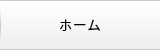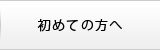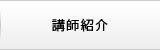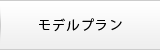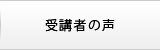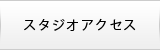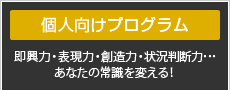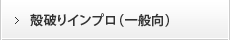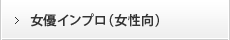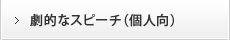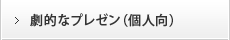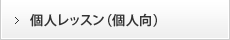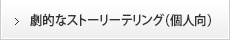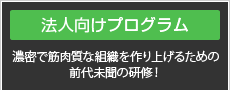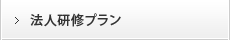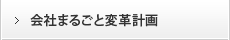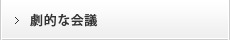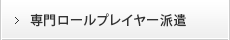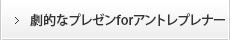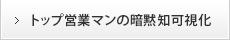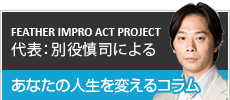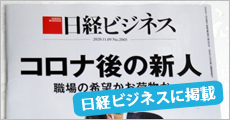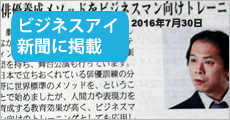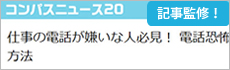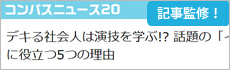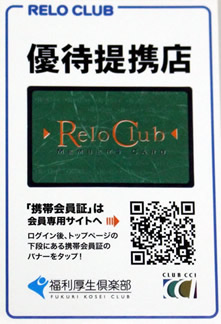カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2019年11月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (2)
- 2015年12月 (1)
- 2015年11月 (2)
- 2015年10月 (4)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (3)
- 2015年3月 (3)
- 2015年2月 (1)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (2)
- 2014年9月 (5)
- 2014年8月 (5)
- 2014年7月 (6)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (2)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (5)
- 2013年11月 (6)
- 2013年10月 (7)
最近のエントリー
HOME > あなたの人生を変えるコラム > アーカイブ > 2015年8月アーカイブ
あなたの人生を変えるコラム 2015年8月アーカイブ
ブライアン・トレーシーのスピーチの技術
アメリカの著名なモチベーショナルスピーカーに ブライアン・トレーシー(Brian Tracy)という人がいます。
日本語に訳された著書もたくさん出ています。
Facebookページの「いいね」数は実に130万です。
日本でもセミナーを行ったことがありますが、ぼくの知人はえらく感動していました。
特に、「なんであんなに長時間話してて、ずっと引きつけられるんだろう」ということをいっていました。
ゴール―最速で成果が上がる21ステップという本と
ブライアン・トレーシーの 話し方入門 ー人生を劇的に変える言葉の魔力 という本をぼくは読んだことがあります。
この「話し方入門」ですが、日本語訳こそ陳腐なものになっていますが、
原語は「Speak to Win(勝つための話し方)」です。
ブライアン・トレーシーのノウハウが詰まっていると思います。
ちなみに読破して、三つのこと以外は、すべてぼくが教えていることと合致する内容でした。
これはのちほどご紹介します。
数字とわかりやすさ
支持を受ける人の話はわかりやすいものです。
この前ご紹介したガイ・カワサキもそうですけど、
ブライアン・トレーシーも、箇条書きで要点をまとめます。
たとえば、「観客をあっと驚かせるパブリックス・スピーキングの8つのテクニック」などといって紹介します。
こういわれると気になりますし、〇つのと言われると、体系化されたお得情報を聞けるという気持ちになります。
また、「~~の調査によると、~~%の人が……で」というように統計上の数値も要所で入れてきます。
アメリカ人がそういうのが好きだというのもあるんでしょうが、説得力を増す技術としては王道です。
達人は這い上がった人たち
おもしろいエピソードとして、
「現在上位10%のスピーカーやセールスマンも最初は下位10%だった」
という話が出てくるのですが、極端だなと思うものの、彼の経験上、本当に這い上がっていった人たちをたくさん知っているのでしょう。
自分が「出来ない」と思い知ることはとてもよいことだということを示していますね。
なぜなら、出来ないからこそ、うまくなろうとして、そのエネルギーによってトップクラスになってしまうのですから。
中途半端に出来る人は、中途半端に上位にいくか、中途半端に下位にいくかの二つなのかもしれません。
ブライアン・トレーシーとの相違点
さて、ブライアン・トレーシーの教えとの相違点3つをご紹介します。
①両腕をだらんとさせるのが基本姿勢だというジェスチャーに関すること
→これは半分同意です。なぜなら、ニュートラルポジションは緊張を覆い隠しますから。
ただ、日本人はだらんと腕を垂らしてもがたいがよくないので、ブライアン・トレーシーほど安定感を出せません。
②歩き回らないほうがいいというジェスチャーに関すること
→これも、ブライアン・トレーシーなら、不動のようにたたずんで安定感を出せるのですが、
人には様々なスタイルがありますし、歩くことで、聴衆は目を動かし、退屈しないので、メリットが多いです。
相当に声と姿勢で引きつけられる人は動かなくても大丈夫でしょう。
③徹底的な準備主義
→半分同意ですが、準備ばかりにおぼれて、本番の力に乏しい日本人は、
即興力を伸ばしていった方が遙かに有益でしょうね。
準備による計算と、本番に強い即興力の二つが合わさると最強だとぼくは考えています。
逆に、実にたくさんの共通点がありました。
これからこの「あなたの人生を変えるコラム」のなかでも、
どこかでブライアン・トレーシーに触れることがあると思います。
皆さんも、なにか読んでみてください。
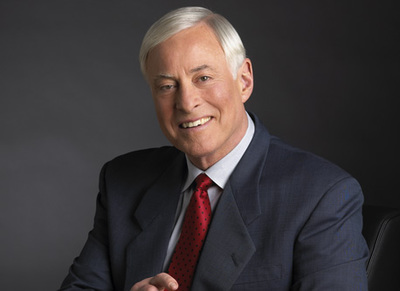
(株式会社ASCEND FEATHER)
2015年8月29日 22:56





相手を知る5分間
虚と実
ビジネスの交流会でのこと。
交流会ではいろいろな人と出会いますが、たいてい名刺交換時の3~5分程度しか、相手のことを知ることができません。
お互いに、自分のやっていることを要約で語り、あとは名刺に書かれている文言で相手を判断するしかありません。
人は、基本的にはその名刺と5分間を信じます。
相手の表情や服装、姿勢、話している内容も相手を知る手がかりになります。
こんな人がいました。名刺にはすごいことがたくさん書かれています。
でも、顔色が悪く、身体もだらしなく太り気味、喋りにも覇気がない。
名刺も書かれている実績の割に手作り感が強く、雑然としている。
後日ブログを見てみたら、どうも「虚」が強そうなのです。
すごいと思われようとしない自制心
人と出会って第一印象が形成されるわずかの時間。
虚像のプロフィールで、相手をすごいと思わせることはできるかもしれません。
しかし、その先には進展していかないでしょう。
これが、騙されやすく、意志薄弱な人であれば、意外なほど「すごい人」という印象を維持できるかもしれません。
だから、怪しい霊能力者などはたくさんいるわけです。
しかし、ビジネスマッチングとなると、本物の実力がないと進展しません。
本当の価値を届けられる人でないと、ビジネスはうまくいかないからです。
未熟でもいいから「実」が伴った生き方をしていくべきです。
そのほうが本人も精神衛生上いいはずですし、人を騙してお金を取っても幸せではありません。
「自分はすごい」という幻想を常に維持しようと「虚」の生き方を続ければ、
性格も歪んでくるのではないでしょうか?
それは幸せではありません。
(株式会社ASCEND FEATHER)
2015年8月20日 10:08





インプロ研修の両輪は「気づき」+「スキルアップ」である
Learning × Performance インプロする組織 予定調和を超え、日常をゆさぶる
という本を読んでいて、
ぼくがなぜ、アメリカ流入系・キース・ジョンストン系のインプロに違和感を感じてきたか、
なぜそれらのワークをやりたいとは思わないかが、結構はっきりしました。
気づきしかないビジネス研修
「教育的な視点から生まれたインプロは、あまり良くない」ということはいってきました。
そこも大きな欠点の理由なのですが、更にいうと、これらのインプロは「気づきonly」だということです。
この「インプロする組織」では、著者の高尾さん・中原さんのインプロ実況収録もあります。
ビジネス研修でどのようにインプロを使っているのかがわかるのですが、
学者の立場、インプロ専門家の立場で、有益な気づきをたくさん与えている一方で、
「スキルアップの視点がまったくない」ことに気づきました。
さすが大学の准教授だけあって、様々なサポートする知識があり、豊かな気づきを与えられています。
しかし、アカデミックな香りが強いのです。
本当の醍醐味はヒューマンスキルの向上
ですから、元はキース・ジョンストンのインプロも「俳優トレーニングから生まれた」といっていますが、
これらを俳優がやるかというと俳優はやりません。
俳優は気づきonlyだと困るのです。スキルアップを一番求めているからです。
ぼくがどうして、「世界の俳優トレーニングから応用したインプロ」と掲げているのか。
それは、「気づき」+「スキルアップ」になるからです。
彼らのインプロトレーニングには、スキルアップという観点が乏しく、
従って、完全に素人向けなのです。
それでは、「元々俳優トレーニングから生まれた」という強みが失われています。
俳優ならではの豊かな表現力や微細な感情描写、体の使い方、発想力、コミュニケーション力
などが彼らのインプロワークでは、十分に導くことができません。
素人向け、一般人向けだから、ややもすれば「なんでもあり」の即興になってしまいます。
ぼく自身も、受講者に高度な演技力は一切求めませんが、
スキルアップしてほしいという観点で提供しています。
気づきは、副産物です。
賛否両論が生まれる
著者の方が大切にしているのが「インプロを教える」ということだそうです。
「インプロを通して何かを教える」のではないと。
これは、ぼくの意見と全く逆です。
インプロを通してたくさんのことを教えることができます。
とはいえ、著者の方も、学者の立場・インプロバイザーの立場からたくさん教えています。
けれど、ビジネスに関することは専門外だから踏み込まないそうです。
本の中で収録されている受講者の感想のなかには、
「ビジネスに直結しないので悩んだ」というものがありました。
実際、ぼく自身も、研修会社などにビジネスインプロ研修を売り込むに当たり、
「ビジネスの落としどころがほしい」と各所で注文をつけられたものです。
ですから、ビジネスのことをよく知り、ビジネスに直結する気づきを与えられるようにしていきました。
結果として、完全体験型で、ビジネスに使える気づき・知識も得られ、スキルアップも得られる
というぼくならではのビジネスインプロ研修が培われていきました。
これからも、他にないこの強みを生かして、機会を頂いた場所で
誰もが満足できる研修を届けていきたいと思います。

(株式会社ASCEND FEATHER)
2015年8月 2日 09:01





1